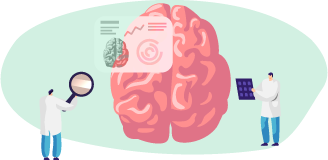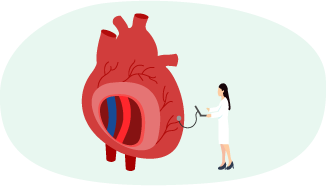診療案内
当院で行っている診療内容や、外来の受付時間などのご案内です。
診療受付時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前08:45~12:00 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 午後13:45~17:00 ※土曜日は13:45~16:00 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
休診日:日・祝・年末年始
- 初診の方は、各受付終了時間の30分前までにお越しください。
- 午前、午後の各受付時間15分前より、順番待ちの発券を開始します。
その他の専門外来を含む、外来担当医はこちらからご確認ください。
外来担当医表18歳以下の受診について
脳神経外科:保護者同伴で受診可 その他の診療科:受診不可
当院の診療について
林脳神経外科メディカルクリニックでは、脳神経外科・内科・消化器内科・在宅医療・人間ドック・各種健診に加え、糖尿病の専門外来を設け、各診療科には専門医師が在籍しています。
より専門性の高い診療・検査をご提供することはもちろん、各診療科が連携し患者さまのお悩みに幅広く対応いたします。
些細なお悩みも、お気軽にご相談ください。
消化器内科(内視鏡検査)
検査の前には消化器内科の診察が必要です。
胃もたれ・胃痛・下痢・便秘の症状などの消化器症状についてご相談下さい。胃カメラ・大腸カメラなどによって消化器疾患の精密検査を行います。
女性看護師が対応しているため、女性の患者さまでも安心して受診していただけます。

在宅医療
当院では、介護事業者の方々との連携を図りながら訪問診療を行っています。患者さまがご自宅で安心して生活を続けられるよう、必要時はクリニックでの検査や地域の病院へのご紹介など、総合的にサポートします。
担当スタッフは、在宅医療の経験が豊富で、患者さまはもちろん、ご家族の方へのサポートも大切にした診療を行っています。
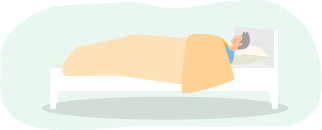
人間ドック・各種健診
ベーシックな人間ドックの他、胸部CTや頭部MRIなどを含んだフルコース、ご希望の検査の組み合わせができるコースも準備しています。また、乳がんドック・子宮がんドック・ブライダルドックなどの女性用のドックも充実しています。
万が一異常が見つかった場合は、当院の外来診療にて各分野の専門医師が診療を行います。
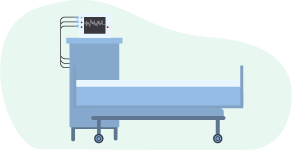
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査・治療
睡眠中に呼吸が止まる、または浅く・弱くなることで、日常生活に障害を引き起こす睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、放置すれば高血圧・脳卒中などの生活習慣病を合併するリスクが高まります。
検査や治療は、おもにご自宅で行うことが可能ですので、早めの受診をおすすめします。

健康管理の第一歩は、身体の状態を知ることから!
定期的な健診・検診で、しっかりチェックすることが大切です。